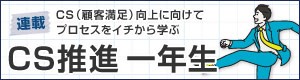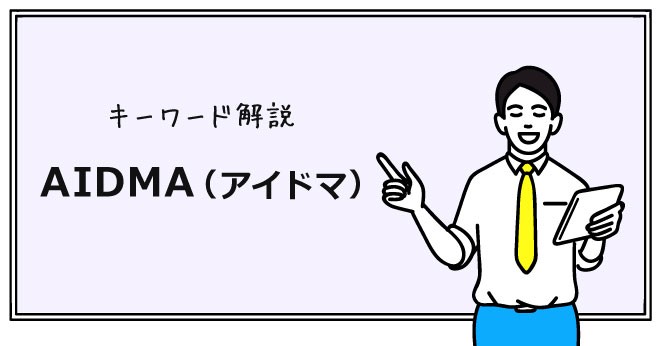
消費者行動を考える際に知っておきたいフレームワークの1つがAIDMA(アイドマ)です。購入までのプロセスと心理状態を把握することで、CS(顧客満足)やマーケティングの施策に役立てることができます。そこで本記事では、AIDMAの概要や活用方法、そのほか、AISAS(アイサス)など類似したフレームワークとの使い分けについて解説します。
今回のキーワード AIDMA(アイドマ)
AIDMA(アイドマ)とは?
AIDMAとは、消費者の購買行動の流れを体系化したフレームワークのことで、アメリカの著作家サミュエル・ローランド・ホールが、1924年に発表した著書「Retail Advertising and Selling(直訳:小売り広告と販売)」で提唱しました。
AIDMAでは、消費者の購買に至るまでの心理プロセスを5つの段階に分類しています。
1:Attention(注意)
2:Interest(関心)
3:Desire(欲求)
4:Memory(記憶)
5:Action(行動)※購買
これら5つの英単語の頭文字を取ってAIDMAと呼ばれていますが、この5段階はさらに「認知段階」「感情段階」「行動段階」の3つのプロセスに大別することができます。
1. 認知段階:Attention(注意)
消費者は商品について何も知らないため、まずは商品を認知してもらうための施策が必要です。テレビCMや新聞・雑誌広告、プレスリリース、インターネット広告など、ターゲットとする消費者の生活スタイルの中において、関心を惹くような方法で施策を行っていきます。
2. 感情段階:Interest(関心)・Desire(欲求)・Memory(記憶)
消費者に「商品に対する好き・嫌い」といった感情から、購入の意思決定を判断してもらう段階です。まだ商品を認知しただけの消費者に対して、その商品に対して「興味を持ち」「欲しいと感じ」「買いたいという気持ちを忘れない(記憶する)」ように促す施策を行っていきます。
たとえば、商品が他社製品よりも優れていると具体的なデータで示したり、イベントを企画して直に商品に触れてもらう機会を作ったりすることで消費者の購買意欲を高め、そして、DMやメルマガなどを送って購買意欲を失わないようフォローします。
3. 行動段階:Action(行動)
消費者が実際に商品を購入しようとしている段階です。消費者が商品を購入するための仕組みを難しいと感じないように、たとえば、公式サイト上からワンクリックで商品が購入できる、あるいは専用はがきに記入・送付するだけで手続きが完了するといった仕組みを検討します。
<身近な具体例>
身近な例として、自家用車を購入するまでのプロセスを考えてみましょう。新型モデルの自動車が発売されたことを知ってから購入するまでには、いくつかの段階を経ています。
|
プロセス |
ステップ |
具体例(消費者の心理や行動) |
|
認知段階 |
Attention(注意) |
テレビCMなどで新型モデルの車が発売されたことを知る |
|
感情段階 |
Interest(関心) |
デザインや機能、乗り心地、価格などについて情報を集めて関心を高める |
|
Desire(欲求) |
他社商品と比較、実物を見る、試乗してみる、欲しくなる |
|
|
Memory(記憶) |
雑誌の試乗記事やDM、メールによるリマインド |
|
|
行動段階 |
Action(行動) |
ローンのシミュレーション |
このように、AIDMAの分類に基づいて消費者の心理プロセスを考えることで、消費者のニーズをより深く理解し、より効果的な広告の作成やマーケティング施策を行うことができるようになります。
AIDMAを活用するメリット
企業のCS担当者やマーケティング担当者は、AIDMAを活用することで、段階ごとの消費者の心理プロセスを把握し、それぞれの段階に合った戦略と施策案を考えることができるようになります。
消費者の購買行動を全体的に漠然と見ていても、マーケティング施策の問題点や課題はわかりません。
しかし、認知から購入に至るプロセスを段階的に分けて評価することで、どの段階に問題があるかを見極めることができるのです。
また、段階ごとに目標を設定し、目標に合ったマーケティング施策を行うことで、消費者を次の段階へ進ませることができるようになり、最終的には、ゴールである「行動」につなげることが可能となります。
AIDMAを活用するときのポイント

AIDMAを正しく活用するためには、5つのステップごとに、以下の「消費者の状態」と「コミュニケーション目標」を十分に理解し達成することが重要となります。
|
ステップ |
消費者の状態 |
コミュニケーション目標 |
|
Attention(注意) |
商品を知らない |
認知度の向上 |
|
Interest(関心) |
商品を知っているが関心がない |
関心度の向上 |
|
Desire(欲求) |
商品に関心はあるが別に欲しくない |
ニーズの喚起 |
|
Memory(記憶) |
商品は欲しいが購入する動機がない |
購入動機の提供 |
|
Action(行動) |
購入する動機はあるが買うタイミングがない |
購入機会の提供 |
また、より効果的にマーケティング施策を行うためのポイントをご紹介します。
Attention(注意)の強化
最終的に「商品の購入」という行動へ進んでもらうためには、最初の認知段階を強化することが重要です。商品を認知した消費者が多ければ多いほど、最終ステップまで進む確率が高くなるからです。
そこで、まずはAIDMAの第一段階である「Attention(注意)」で、しっかりと消費者のニーズに応える広告を展開するといった施策を行うことが必要となります。たとえば、第一段階の認知を増やすために、広告予算を大きめに確保するといったことが考えられるでしょう。
目標(KPI)の設定
AIDMAを活用した手法では、段階ごとに目標の設定と結果を評価して、達成していない場合は改善策を行っていくという工程を繰り返すことになります。そこで、正しく評価を行うために、KPI(重要業績評価指標)を設定して目標の達成度合いを確認します。
ペルソナに適したコンテンツの提供
AIDMAをベースに商品を購入するまでのプロセスをストーリー仕立てで考えていくと、消費者の人物像(ペルソナ)を知ることができます。
さらに、そのターゲットが求めているのは何か、悩んでいることは何かということを明確にすることができるため、消費者のいる段階に応じたコンテンツを提供することが可能となります。
適切なタイミングで、その状況に適したコンテンツが提供できれば、消費者は次の段階へと進み、やがて購入へと近づいていくのです。
人気アーティストやヒット商品から見るAIDMAの事例
続いて、優れたマーケティング戦略を展開しているアーティストや商品をAIDMAの視点から紹介します。
事例1:NiziU(ガールズグループ)
1つ目の事例は、2020年、エンターテインメント業界で話題を集めたグローバル・ガールズグループ「NiziU(ニジュー)」を取り上げてみます。
NiziUは、韓国の大手事務所・JYPエンターテインメントと日本のソニーミュージックとが共同で開催したオーディション・プロジェクト『Nizi Project』から結成された9人組です。テレビとSNSを軸に人気を高めていった彼女たちのマーケティングも、以下のようにAIDMAで紐解くことができます。
|
Attention(注意) |
JYPエンターテインメントとソニーミュージックの合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project」の募集が開始。この時点ではまだ認知は低いが、オーディションの模様をドキュメンタリー番組としてHuluで配信したり、日本テレビ系『スッキリ』で定期的に取り上げてもらったりするなど、メディア戦略が開始される。 |
|
Interest(関心) |
配信されるドキュメンタリー番組以外でも、芸能人たちがさまざまな媒体で「Nizi Project」を話題にし、応援していると公言する。プロデューサーのJ.Y. Park氏のモノマネなども話題となり、元々興味のなかったユーザーの関心を引く。 |
|
Desire(欲求) |
番組の枠を超えて、オーディションのドラマ性や候補生のパーソナリティ、パフォーマンスのクオリティが強調される。 |
|
Memory(記憶) |
Huluで独占配信だった番組が、後追いの形でYouTubeでの無料配信がなされ、気軽に見られるようになる。プロジェクトのゴールが半年という期限つきであることから、SNSでの情報発信も拡散されるようになり、選考終盤になるほど注目を浴びる。 |
|
Action(行動) |
候補生のメンバーに1日1票だけ投票できる「虹かけランキング」を導入し、番組とファンが連動。リアルタイムで順位が見られるドキドキ感を演出しながら、プロジェクトに気軽に参加できるような仕組みをつくる。“プレデビュー”となるデジタルミニアルバム『Make you happy』発売時には、TikTokで動画投稿キャンペーンを行うなどファン参加型の施策を実施。表題曲の「Make you happy」を印象付ける“縄跳びダンス”が話題を呼んだ。 |
最初のAttention(注意)は、オーディションの告知からですが、認知の火をつけたのは、朝の情報番組『スッキリ』(日本テレビ系)で密着取材が開始されたタイミングでしょう。Huluユーザーにしか目に触れなかった候補生たちとオーディションの模様を、マスメディアに届けるという一手でした。
こうしたなか、他のテレビ番組でも芸能人がこぞって「見ている」と発信するようになり、認知と感心を高めていきます。
さらに、さまざまな媒体にて、プロデューサーのJ.Y. Park氏の人柄や、メンバー候補生の目標に向かう姿が取り上げられました。この様子を見て「自分もついていかなくては」という気持ちになった視聴者もいることでしょう。
その後、Huluでの先行配信に加え、過去の番組の内容がYoutubeで毎週公開されるようになり、それまでの経緯を追っていなかった人たちも気軽に『Nizi Project』に触れられるようになります。
「選考」という大きな目標を目前にして、ますます盛り上がるなか、Memory(記憶)の段階を経て、ファンには「虹かけランキング」という応援しているメンバーに毎日1票だけ投票できる機会を与えられ、『Nizi Project』に直接参加することができるようになりました。
こうしたファンとの共働作業によって誕生したのが「NiziU」だと言えます。
>NiziUのプロフィールや関連記事はこちらをチェック(外部リンク)
事例2:檸檬堂(レモンサワー)
2020年、多くのマーケターから注目を浴びた商品の1つが、コカ・コーラシステムのレモンサワー『檸檬堂』です。競合ひしめく缶チューハイ市場の中で、他の商品とは異なる存在感を放ち、話題になりました。そのマーケティングをAIDMAで分析すると以下のようになります。
|
Attention(注意) |
果実や飛び散る水滴など「フレッシュさ」を強調するようなパッケージが多かった、これまでの缶チューハイと比べ、酒屋の前掛けを模すような紺色のパッケージや、「檸檬堂」という漢字を用いたブランドネームで差別化を図る。 |
|
Interest(関心) |
「鬼レモン」「塩レモン」「定番レモン」「はちみつレモン」など「レモン」だけに特化した複数の商品を展開。アルコール度数や味を変えることで、消費者の興味を喚起。また、コカ・コーラ社が初めてアルコール飲料の企画から販売までを行ったという話題性も関心を抱かせた。 |
|
Desire(欲求) |
初期は九州限定で販売されていた。SNSなどで話題になるものの、九州限定のため、それ以外の地域の人たちは欲しくても手に入らなかった。出張で購入しようと考えたり、九州に住む知人を経由してお願いするなど、入手方法を工夫する必要があった。 |
|
Memory(記憶) |
全国発売が決まると、全国規模のテレビCMを展開する。CMには、パッケージデザインと統一された世界を演出するように、俳優の阿部寛さんを起用しつつ、質の高さと和風を想起させる。 |
|
Action(行動) |
恵比寿に『檸檬堂』とおつまみを無料で提供する期間限定店舗をオープンして試飲機会を設けた。また、全国発売に先立ち、一部飲食店で檸檬堂をメニューとして“先行提供”する試みも。 |
まず注目すべきはパッケージです。『檸檬堂』は、缶チューハイでよくある「果実」や「水滴」を描いたフレッシュさを強調したデザインではなく、酒屋の前掛けを模すような紺色のパッケージになっています。これにより、店舗に訪れた消費者の注意(Attention)を引きつけました。
そして消費者は『檸檬堂』に、「鬼レモン」「塩レモン」「定番レモン」「はちみつレモン」など4種類の商品があることに気が付きます。(※発売当初)レモンサワー専門ブランドとしてレモンだけに特化した商品展開に「よほど自信があるのか」と感心(Interest)を抱くようになります。
また、「コカ・コーラ社が初めて発売するアルコール飲料」ということ、初期は九州限定販売ということで、多くのユーザーが手に入れられない段階で、SNSなどで話題になります。
その後、一気に全国展開し、パッケージデザインと同一の世界観を持った、落ち着いた雰囲気のテレビCMを放送し、『檸檬堂』を視聴者の記憶(Memory)に残します。さらに試飲ができるような場の提供や、一部の飲食店でメニューとして全国発売前に“先行提供”するなど、消費者が『檸檬堂』を試せる環境を作り、たちまちヒット商品となりました。
※参考サイト:“九州No.1”のレモンサワー「檸檬堂」全国発売、日本コカ・コーラ初のアルコール飲料|食品産業新聞社ニュースWEB(外部リンク)
AIDMAはもう古い? AISAS(アイサス)との違い
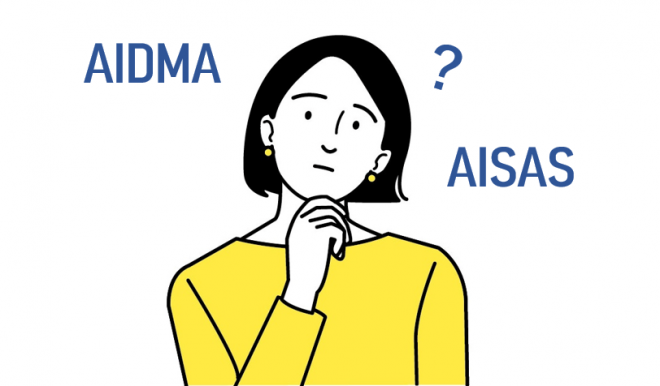
インターネットが普及する以前は、消費者が商品情報を得るにはテレビや新聞広告などのマスメディアに限られていたため、消費者行動を分析するにはAIDMAが最適でした。
しかし、2000年代になりインターネットが普及していくと、消費者の購買行動に変化が起きました。消費者はこれまでマスメディアを通じて商品情報を受け取る立場にありましたが、インターネットで自ら情報を探すようになり、さらに購買後には情報を広める行動をするようになりました。
このような背景から、購買行動を以下の5つのプロセスに分類したフレームワークが広く知られるようになったのです。
1:Attention(注意)
2:Interest(関心)
3:Search(検索)
4:Action(行動)
5:Share(共有)
5つの英単語の頭文字を取って、「AISASの法則」と呼ばれるこの消費者の購買行動モデルは、電通が提唱したものです。AIDMAからDesire(欲求)とMemory(記憶)がなくなり、代わりに消費者の行動として検索(Search)と共有(Share)が追加されています。
では、もう少し詳しくAISASの各プロセスについてご紹介します。
【AISASにおける具体的な行動】
1:Attention(注意)
消費者の Attention(注意)を喚起し、商品を認知してもらうことを目的としています。
2:Interest(関心)
商品を認知した消費者に対し、さらに商品への Interest(関心)を促すことを目指して、詳しい情報発信をしていきます。
3:Search(検索)
消費者は自らインターネット上の口コミや比較サイトを活用して、他社の競合製品と比較・検討をはじめます。企業側では、消費者の情報ニーズに網羅的に応えることが必要です。そのうえで、自社の商品の優位性をアピールすることが求められるようになります。
4:Action(行動)
あらゆる情報を提示して消費者に選んでもらい、初めて購入という行動につながります。また、購入のしやすさも大切な要素です。
5:Share(共有)
そして、最後のステップが Share(共有)です。満足や不満だけでなく、消費者それぞれの意見がSNSなどで共有されるようになります。こうした情報が、次の消費者の判断材料となります。商品に不満があり、悪い口コミが広がると、その後の売り上げにも影響が出ます。そこで、消費者の口コミや要望を真摯に受け止め、誠実に対応することが重要です。
【ニーズ・状況別に紹介】類似した消費行動フレームワーク
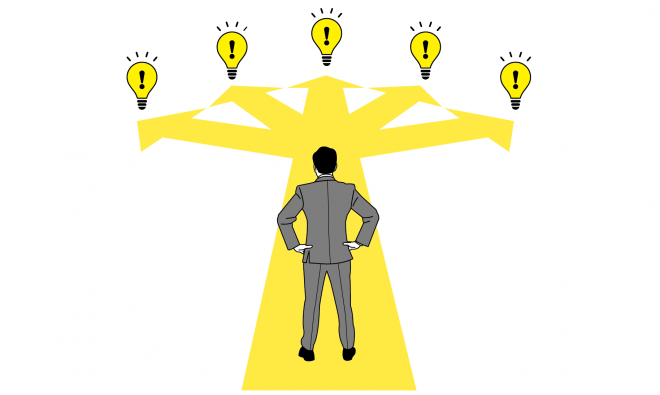
現在では、AIDMA以外にもさまざまな購買行動フレームワークが誕生しています。重要なポイントは、それらのフレームワークを状況に応じてうまく使い分けることです。そこで、一般的によく知られている購買行動フレームワークについて、ニーズや状況別にご紹介します。
長期的なマーケティングの場合は「AMTUL(アムトゥル)」
AIDMAは短期的な1回の消費者の購買行動プロセスを示すものですが、もう少し長期的な目線で継続的な消費者の購買心理をプロセス化したものにAMTUL(アムトゥル)があります。
AMTULは1970年代に経済評論家の水口健次氏が提唱しました。
Aware(認知)
Memory(記憶)
Trial(試用)
Usage(本格的な使用)
Loyalty(固定客)
AMTULの一番大きな特徴は、顧客ロイヤルティという概念を取り入れていることです。消費者は商品に対して、どれだけ愛着を持ち、どれだけ信頼しているかによって、継続的にその商品を購入します。
逆に、愛着度や信頼度が低ければ、ちょっとした要因で消費者はすぐに他社商品へ乗り換えてしまうことが考えられます。
そこで、5つのプロセスのうち3つ目からのTrial(試用)、Usage(本格的な使用)、 Loyalty(固定客)という消費者の購買後を段階的に分けて施策を実施し、その結果、設定したコミュニケーション目標が達成できたかどうかを、マーケティング調査を行って判断します。
ダイレクトマーケティングの場合は「AIDCA(アイドカ)」
AIDMAと同じく、ユーザーの購買決定プロセスをフレームワーク化したAIDCA(アイドカ)は、1920年代のアメリカの応用心理学者E・K・ストロング氏によって提唱されました。
AIDCAではAIDMAの5つのプロセスから、Memory(記憶)の代わりにConviction(確信)を用います。Conviction(確信)とは、その商品は確かに購買する価値があると信じることです。
Attention(注目、商品やサービスの認知)
Interest(関心)
Desire(欲求)
Conviction(確信)
Action(行動)
AIDCAではConviction(確信)が重要とされていますが、これは、商品に対する認知が低かったとしても、その商品には購入する価値があると判断してもらえれば購入につながるからです。
とはいえ、消費者は商品の価値を理解しても、それだけでは購買につながらない場合も多く、次のプロセスへ進むための施策が重要となります。
そこで、広告だけでなく、利用者のレビューを紹介したり、有識者の評価を掲載したりするなど、消費者の商品に対する評価をより強固なものにし、確信へと促していく施策が重要となります。
そのため、AIDCAはダイレクトマーケティングで活用されます。一般的な広告よりも情報を盛り込み、その商品が欲しいと思った後に、購入することは正しい選択だという確信の段階を経て、購買へと進むような流れになります。
店頭プロモーションの場合は「ARCAS(アルカス)」
ARCASは、店頭プロモーションで用いられるマーケティングの消費行動プロセスモデルで、広告代理店である電通が提唱しています。
Attention(気づき)
Remind(思い起こし)
Compare(比較)
Action(行動)
Satisfy(満足)
ARCASは消費者の来店から購入に至り、さらに再来店するまでの行動を整理したものです。
消費者は売り場で商品に気づいたとき、今まで見聞きした広告を思い起こして、購入する動機を獲得します。さらに、他社商品と比較して理論的な根拠を元に購入に至り、消費者がその商品に満足すれば再来店につながります。
このとき、消費者は商品に対してだけでなく、商品の試食や実演、販促POPなどのプロモーションや、スタッフの接客対応・サービスなども加味して満足度を判断します。
また、基本的な部分はAISASとまとめることができますが、ARCASでは消費者が来店する前のアプローチも重要とされています。そこで、インターネット上のデジタル領域と連動するプロモーションで、消費者に来店を働きかけるO2O(Online to Offline)なども有効です。
インターネット時代における「共有」に着目する場合は「AIDEES(アイデス)」
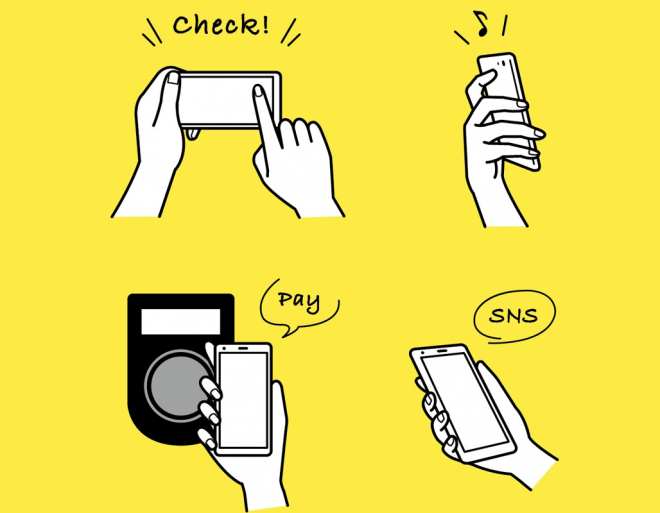
AIDEESは、元東京大学大学院教授の片平秀貴氏が提唱する消費者の購買行動プロセスモデルです。
消費者が商品を認知してから購入した後の行動も含めてプロセスモデルにしたもので、SNSやブログによって個人による情報発信が一般的となったインターネット時代において、「他者と情報を共有したい」という消費者心理もとらえています。
Attention(注目する、知る)
Interest(関心を持つ)
Desire(欲しいと感じる)
Experience(体験する、購入する)
Enthusiasm(感動する、心酔する)
Share(共有する、推奨する)
最初の3つのプロセスはAIDMAと同じですが、4つ目のExperience(体験し購入する)に続くEnthusiasm(感動)とShare(共有)が特徴的なプロセスといえます。
商品を購入した消費者は、満足度が感動・心酔するレベルであれば、情報を発信し他者と共有するような行動を起こします。
SNSツールの普及により、情報共有のつながりが消費行動の1つの要因にもなっていますので、商品に対す好感度が口コミとして広がれば、大きなイメージ作りになっていきます。
ソーシャルメディアの影響力に着目する場合は「AISA(アイサ)」
AISAは、ソーシャルメディア・ソーシャルアプリ事業を展開しているガイアックスが提唱した購買決定プロセスモデルの1つで、その特長はソーシャルメディアの影響力に着目しているところです。
Attention(注目する、知る)
Interest(関心を持つ)
Social Filter(ソーシャルフィルター)
Action(行動)
AISASの1つ目のSは「Search(検索)」ですが、AISAのSは「Social Filter(ソーシャルフィルター)」を意味します。
これまで、インターネット上で商品に関する情報を検索する場合は、Googleなどの検索エンジンが大きく関与してきました。
しかし、FacebookやTwitterなどを使用したソーシャルサーチの件数がGoogleなどの検索エンジンを利用した検索件数を上回ってきたことや、他社の商品に対する反応を見たうえで購買決定をするという傾向が見られるようになってきました。
つまり、SNSで受動的に集まる情報がメインストリームになってきているのです。そのようなソーシャルサーチ、ソーシャルフィルターの時代に対応すべく考案されたモデルがAISAなのです。
AIDMAは人間心理の本質をつかんだフレームワーク
AIDMAは100年前に提唱された消費者の購買行動をフレームワーク化したものです。ネット社会が進んだ現在では古いといわれるのも仕方がありませんが、購入に至る人間の心理の本質をつかんでいることから、いまだに活用されています。
認知から購入までの各段階で、それぞれに適した施策を打ち出し、評価と改善を続けていくという手法はいつの時代にも有効といえるでしょう。
今後、社会が変化したとしても、人間の本質は変わらないことから、マーケティングに携わる人はAIDMAの考えを身につけておく必要があります。そのうえで、時代のニーズに合わせてほかの手法も取り入れるようにしましょう。
>CS・マーケ担当者必見!「キーワード解説」記事一覧